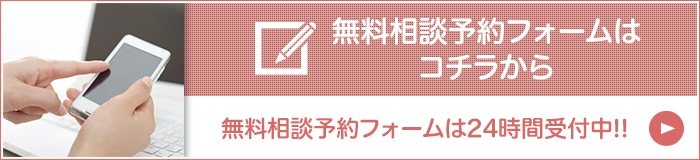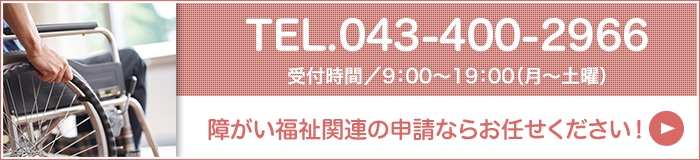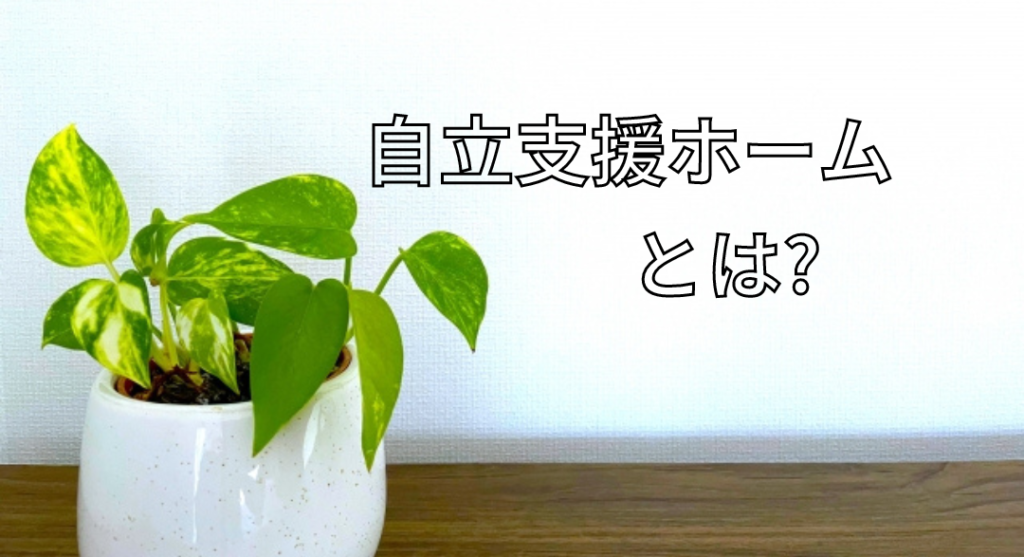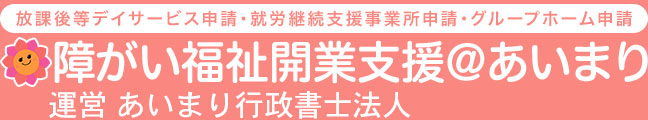サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者になるには?
このページでは、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者になるためには、どういった要件が必要
になるのか。や、令和5年6月30日のサービス管理責任者等研修の制度の改正についても解説していきたい
と思います。
障がい福祉事業には、このサービス管理責任者、児童発達支援管理責任者の人を必ずおいて常勤でお仕事を
してくださいね。という規定がある事業があります。
その職員さんが欠如すると、大幅な減算(報酬の◯%カットなど)があり、事業の継続が危ぶまれます。
事業の継続できないということは、サービスの提供が継続できないので、利用者さん(お子さんと保護者)
が困ることになります。
そういった事態におちいらないように、資格の制度自体から知っていきましょう。
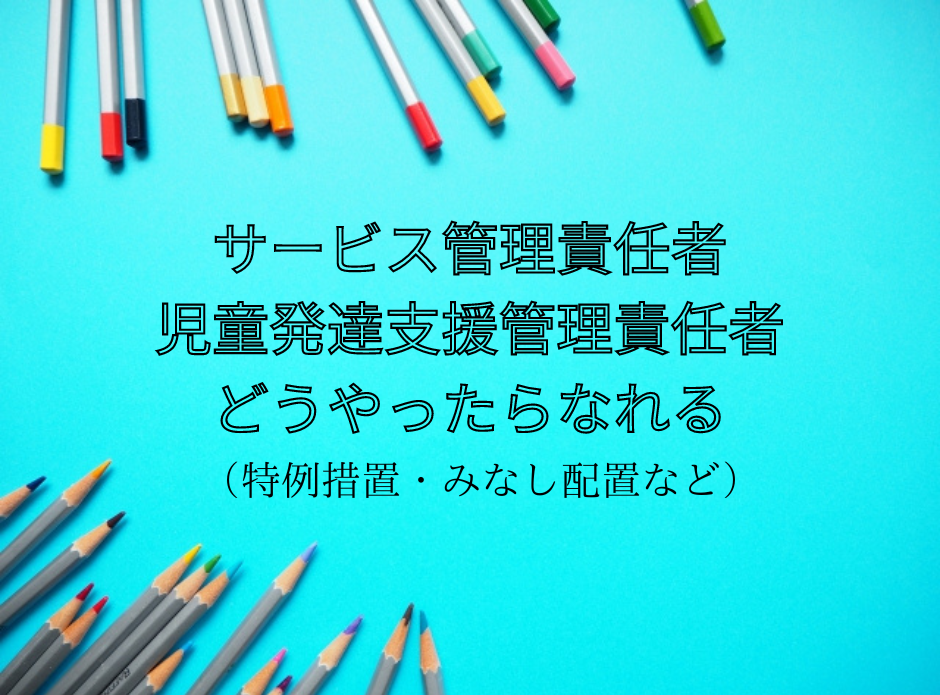
最後の方に、令和5年6月30日の制度改正にも触れていますので、
そちらを知りたいという方も、下の方までお読みください。
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者とは?
■サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者の、大きくわけた基本的な業務です。
(1)個別支援計画の作成
(2)計画書に基づき支援員さんへの指導・助言
(3)保護者や関係機関との連携・調整
(4)その他に関する業務
※サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者さんは、管理者と兼務することも多く、その場合は、事業
所全体の管理業務や運営業務など、多岐にわたります。
※お仕事内容については、また別のページで詳しく触れたいと思います。
サビ管、児発管になるには2つの要件を満たすことが必要
サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者になるためには、
1️⃣ 実務経験要件
2️⃣ 研修修了要件
の両方を満たすことが必要です。
1️⃣ 実務経験要件とは、どんなものですか? ※注意あり
■ここで一つ注意点です。
サービス管理責任者と、児童発達支援管理責任者で、それぞれ実務経験と認められるもの異なってきます。
障害者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験が
以下の①~③のいずれかを満たしていること。 なお、実務経験については、サービス管理責任者と、児童発
達支援管理責任者に就任する時点で、経験年数を満たしていることが必要になります。
①相談支援業務及び直接支援業務の期間が通算して5年以上
②直接支援業務の期間が通算して8年以上
③国家資格の期間が通算して3年以上
↓それぞれの実務一覧についてはこちらでご確認ください
2️⃣ 研修修了とは、何ですか? ※特例措置あり
■サービス管理責任者等 基礎研修 修了しており、2年以上の実務要件(OJT)実践研修を修了しているこ
とが必要です。
・指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等
・障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定めるもの
サビ管、児発管の特例措置とは? OJT版
令和5年6月30日付けで、厚生労働省より事務連絡がだされました。
「サービス管理責任者等に関する告示の改正について」にて、サービス管理責任者等研修の制度の改正があった
のは記憶に新しく、まだ、浸透しておりませんので、しっかりおさえておきましょう。
今回の制度改正において、その要件を満たしている者で、指定権者に届出を行っている場合は、例外的に実務経験
(OJT)を「6ヶ月以上」の期間で実践研修を受講することが可能となりました。
2年のOJTが、6ヶ月以上のOJT期間となります。
そのためには、その要件を満たし、指定権者に届け出が必要となってきます。
※ 特例措置 要件とは?
新たに、基礎研修受講開始時において、既に実務経験者である者が、実践研修を受講するための
実務経験(OJT)として障害福祉サービスに係る個別支援計画の作成の一連の業務に従事し、その
旨を指定権者に届け出ている場合は、例外的に「6月以上」とします。
1️⃣基礎研修受講開始時に、すでに実務経験者である
2️⃣障害福祉サービスに関わる個別支援計画の作成の一連の業務に従事している
3️⃣そしてその旨を指定権者に届け出している

サビ管、児発管の特例措置とは? みなし配置版
また、今回の改正には、やむを得ない自由によりサービス管理責任者等がかけた場合にも、特例の措置が
されました。サービス管理責任者等がやむを得ない事由により欠如した場合に実務経験者をサービス管理
責任者等とみなして配置する措置については、現行制度上、サービス管理責任者等の欠如時から1年間と
しております。
今回、基礎研修修了者については、個別支援計画の作成に関して一定の知識・技能等を習得していること、
また、事業所内でのサービス管理責任者等の養成を進める観点から、従前のやむを得ない事由(※)によ
る措置(1年間)に加え、以下のいずれの要件も満たす者について、当該者が実践研修を修了するまでの
間に限り、サービス管理責任者等とみなして配置可能(最長2年間)としました。
1️⃣~3️⃣の要件を満たす必要があります。
1️⃣実務経験要件を満たしていること
2️⃣ サービス管理責任者等が欠如した時点で既に基礎研修を修了済みであること
3️⃣ サービス管理責任者等が欠如する以前から当該事業所に配置されていること
※ やむを得ない事由については、サービス管理責任者等が退職、病休など事業者の責に帰さない事由に
より欠如した場合であって、かつ、当該事業所にサービス管理責任者等を直ちに配置することが困難な
場合を想定している。
<やむを得ない事由とは>
①退職、病休など、事業者の責に帰さない事由により欠如
②当該事業所に、サービス管理責任者等を直ちに配置が困難
①と② どちらも必要です。
おわりに
現在、障がい福祉事業所様からよく聞くのは、サービス管理責任者等がやめてしまうと、なかなか次の人が
募集をかけてもこなかったり、きても定着がしずらい。。。とご相談をうけます。
ですので、事業所内で、サービス管理責任者等を養成していくことにはなるのですが、なにせ、基礎研修の
受講を希望しても、応募者が多数すぎて、研修が受講できない。。。となげく事業者さんを目の当たりにし
ています。
最初にも触れましたが、障がい福祉事業の継続には、サービス管理責任者等の安定的な雇用と、人材の確保
が必要になってきます。
ですので、今回の(令和5年6月30日改正)の特例措置など、該当する事業所さんは、お忘れなく必要な対応
をお願いいたします。 事前に、届け出など必要な要件があります。
そして、平成 30 年度までに研修を修了したサービス管理責任者等が、今後、この資格を継続して、更新する
ためには、令和5年度末までに初回の、更新研修を受講する必要がありますので、その点もあわせて、ご注意
をお願いします。

参考:サービス管理責任者等に関する告示の改正について
(令和5年6月30日厚労省・こども家庭庁事務連絡)

千葉 直子
2023 年 3 月 障がい福祉専門の「あいまり行政書士オフィス」 へ事務所名を変更
専門分野:障害福祉
高校・大学とボランティア部に所属
福祉系大学を卒業
【セミナー実績】
障害福祉行政書士のための法令と事例解説
行政書士向けコミュニティでのセミナー