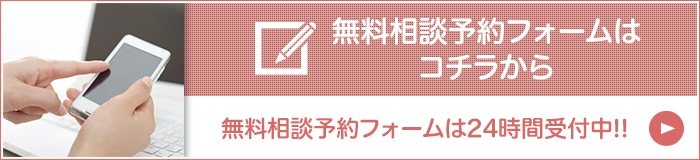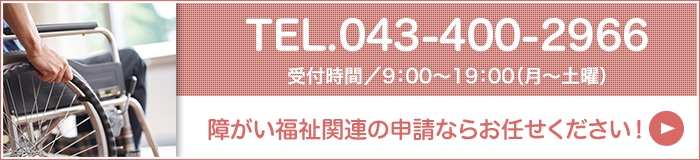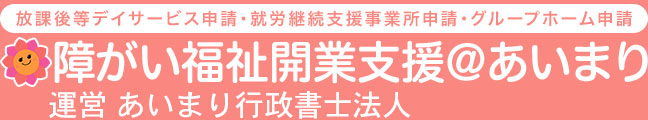児童発達支援を開業するには
児童発達支援(障害児通所支援)を開業を検討するにあたっては、まず、関係法令などについても把握し、
児童福祉法の趣旨(目的・基本理念)十分に理解した上で、「法令等を遵守し、適切な事業運営及び障害児
への適切な支援の提供ができる体制が整っているか」という観点から見ていくことが大切です。
なぜかといいますと、国費の投入された障害福祉事業は、法令に沿って事業制度が進められており、
法令を遵守しないと、返金対象や、最悪のことを想定しますと、事業を停止などリスクがあるからです。
それと同時に、事業計画や、収支予算、人員募集、建物や立地、利用者さん集め、支援計画や内容、
開業時にはたくさんのことを進めていく必要があります。

また、児童発達支援事業所で働いてくれる従業員さん達にも、障がいのあるお子さんに対する適切な支援
の提供を行えるよう、関係法令や義務化されたポイントなど、周知をしていく必要が求められています。
児童発達支援 開設のための関係法令を押さえましょう。
児童発達支援事業所には、様々な法令、条例やガイドライン、規定があります。
①児童福祉法
②児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例
③児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
④児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例について
⑤児童発達支援ガイドライン

すべての把握して、おさえることはむずかしいですが、大切なところは、当サイトでもまとめていきますので
またご紹介させていただきます。
児童発達支援の”指定申請”の流れ
![]()
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく介護給付
訓練等給付及びサービス利用計画作成、児童福祉法に基づく障害児通所支援(児童発達支援事業所)の
サービスを提供するためには、知事(指定権者)の指定を受ける必要があります。

知事(指定権者)の指定 を受けて初めて、事業が開始できます。
障がい福祉事業を開業するには法人格が必要です
・障がい福祉事業施設を開設するには、法人格が必要になります。
■法人とは??
⇒法人とは、世間一般でいう代表的なものは”株式会社”になります。
法人の種類には、株式会社や合名会社、一般社団法人やNPO法人など、さまざまな種類があります。
それぞれ特徴があり、設立手続きの複雑さ、設立にかかる費用、事業拡大にむけての法人格の特性もあります。
例えば、株式会社には株主がおり、営利を目的としています。一般社団法人の非営利型や、NPO法人など
非営利な事業に適した法人もあります。
その法人によって、助成金が使えたり、補助金が使えなかったり、融資の面でも差が出てくることがあるので
最初に事業計画をしっかり立てて、法人を作っていきましょう。
■障がい福祉事業でみられる法人格の種類
①株式会社
②一般社団法人(営利型・非営利型)
③NPO法人
④合同会社
⑤社会福祉法人

![]()
法人等の目的について申請者(法人等)の定款・寄付行為等で、
目的の条文には、指定を受ける全事業について、法的根拠を必ず明記する必要があります。
※手続の終了していないものは申請を受理してもらえませんのでご注意ください。(千葉県)

千葉 直子
2023 年 3 月 障がい福祉専門の「あいまり行政書士オフィス」 へ事務所名を変更
専門分野:障害福祉
高校・大学とボランティア部に所属
福祉系大学を卒業
【セミナー実績】
障害福祉行政書士のための法令と事例解説
行政書士向けコミュニティでのセミナー